公開日 2025/04/10
【医師解説】赤ちゃんのゲップはいつまで必要?|げっぷを上手にさせる方法

目次
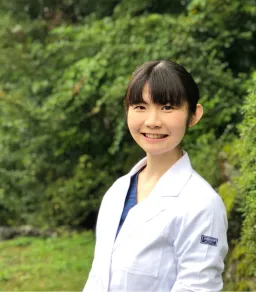
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
赤ちゃんを授乳した後、パパやママが行う大切なことの1つが「ゲップを出してあげること」です。
ゲップを出してあげることは、赤ちゃんが母乳やミルクと一緒に飲み込んでしまった空気を外に出すために行う大切なことですが、「赤ちゃんのゲップ出しはいつまで必要なのか」「思うように出してあげられないときはどうすればいいのか」など、疑問を感じているパパやママも多いのではないでしょうか。この記事では、赤ちゃんにゲップが必要な理由や上手に出してあげるためのコツ、そして赤ちゃんのゲップを手伝う期間について詳しく解説します。
赤ちゃんにゲップが必要な理由とは?
赤ちゃんのゲップは、母乳やミルクと一緒に取り込んだ空気を外へ出す大切な働きがあります。赤ちゃんは未成熟な胃の構造をもつため吐き戻しをしやすく、パパやママのサポートが欠かせません。ここでは、赤ちゃんのゲップについて基礎知識や上手に出すコツを解説します。
赤ちゃんの吐き戻しはいつまで続く?原因や対処法対処法について
なぜ赤ちゃんは空気を飲み込むの?
生後間もない赤ちゃんは、母乳やミルクを飲むと同時に空気も一緒に飲み込みやすいとされています。これは、吸う力の加減が十分にコントロールできないことや、唇の密着度合いが不安定なことなどが原因といわれています。赤ちゃん自身もまだ母乳やミルクの飲み方を学習中の段階なので、上手く飲み方を調整できないことも多いのです。そこでパパやママが赤ちゃんがゲップを出せるようにお手伝いしてあげる必要が出てきます。
赤ちゃんにゲップをさせてあげる理由
授乳後にゲップを出してあげるのは、胃に溜まった空気を外に逃がしてあげることで吐き戻しのリスクを減らすためです。空気が溜まったままだと、ちょっとした刺激や体勢の変化でも母乳やミルクを一緒に吐いてしまいやすくなるといわれています。
また、吐いた液体が気管に入り込んでしまうと、むせたり、息がしづらくなってしまうこともあります。さらに、胃に空気が多く溜まっていると苦しく感じるため、赤ちゃんが泣いてしまうケースもあるでしょう。こうした事態を防ぐために、赤ちゃんにゲップをさせてあげる必要があります。
ゲップがうまく出ないときのサインとは?
授乳後に赤ちゃんが唸るように声を上げたり、しきりに身体をよじって嫌がるような仕草を見せたりする場合は、胃の中に溜まった空気が原因で不快感を覚えているのかもしれません。また、急に泣き始めたり落ち着きがなくなったりするときも、ゲップが出ていない不快感を訴えている可能性があります。もちろん、空腹やオムツの不快感、抱っこしてほしいからなど、赤ちゃんが泣き出す理由は色々ありますが、授乳後まもなくの場合には「ゲップが出ていないサインかもしれない」と意識してあげると適切に対処しやすくなるでしょう。
吐き戻しや誤嚥のリスクを防ぐために
赤ちゃんの胃は大人に比べて形状がまっすぐなため、飲んだ母乳やミルクが逆流しやすいといわれています。とりわけ生後0ヶ月から3ヶ月くらいまでは、逆流防止の弁の機能を持つ筋肉が未成熟なために、飲んですぐに寝かせると口元からミルクが溢れ出てしまうことも珍しくありません。少しなら心配いらない場合がほとんどですが、量が多かったり勢いが強い場合には誤嚥の危険が高まります。ゲップを出させてあげることで、このような吐き戻しリスクを軽減できる可能性があるのです。
赤ちゃんのゲップの出し方とコツ

赤ちゃんのゲップを上手に出すためには、適切な姿勢や方法を知ることが大切です。赤ちゃんに合わせた工夫をすることで、よりスムーズにゲップを促せるようになります。ここでは、ゲップを出しやすい姿勢や具体的な方法、時間の目安について詳しく解説します。
基本は縦抱きスタイル
赤ちゃんがゲップを出しやすい基本の姿勢は、パパやママの肩に赤ちゃんの頭を乗せて縦抱きにすることです。このとき赤ちゃんの顔はやや横を向け、呼吸が妨げられないよう気を配りましょう。
まだ首がすわっていない時期は、必ず首を支えながら赤ちゃんの体を安定させる必要があります。パパやママが椅子に腰掛けて浅めに座り、赤ちゃんが背筋をなるべくまっすぐ保てるように抱き上げると、胃から空気が上に移動しやすくなります。
首すわりってどんな状態?いつ首がすわるのか、確認のポイントや促す運動をご紹介
背中のさすり方・叩き方のポイント
ゲップを出すために背中をトントンするときには、手のひらを少し丸めて、優しく一定のリズムで叩くのがコツです。平手でパチパチ叩くと赤ちゃんが驚いてしまったり、必要以上に刺激を受けてしまったりすることがあるので、気をつけましょう。
叩く代わりに背中をさする方法もあります。どちらの方がゲップしやすいかは赤ちゃんによって異なります。赤ちゃんの反応を見ながら、安心しているようなら続けてみる、怖がっているようなら別の方法に切り替える、といった柔軟さが大切です。
ゲップを促すタイミングの見極め方
ミルクを勢いよく飲む赤ちゃんや、母乳を一気に吸う赤ちゃんの場合、短い時間でも空気をたくさん飲み込んでいる可能性が高いです。そのため、授乳途中でもこまめにゲップを促してあげると良いでしょう。
ゲップを促してから、実際にゲップが出るまでの目安は、5分程度といわれています。5分以上続けてもゲップが出ない場合は、赤ちゃんが疲れてしまうことがあるので、一度切り上げましょう。
他の姿勢(座らせる・うつ伏せ)も試してみよう
抱っこの姿勢でなかなかゲップがでない場合は、他の体勢も試してみるといいかもしれません。例えば、赤ちゃんをパパやママの膝の上でやや前かがみに座らせて背中をさすってあげたり、膝の上にうつぶせぎみに乗せてみたりしてみるとゲップが出やすくなることがあります。
大人でも座っているときとうつぶせで休んでいるときとでは空気の抜け方が違うのと同じで、赤ちゃんも姿勢によって空気の通り道が変化します。最初はうまくできなくても、少しずつ赤ちゃんの反応を見ながら、苦しくない体勢を探してあげるとよいでしょう。
赤ちゃんのゲップ出しはいつまで?月齢別の目安

赤ちゃんが成長し、気道が発達すると、ゲップを出してあげる回数も減っていくことがほとんどです。ゲップを出させてあげなくてよくなる時期には個人差があり、赤ちゃんの様子を見ながら進めていくことが大切です。
新生児期から生後3ヶ月頃まで
新生児期から生後3ヶ月頃までは、「ゲップを出すお手伝い」が特に必要な時期と考えられています。
まだ首もすわっていない赤ちゃんは、母乳やミルクと同時に吸い込んだ空気を自力でコントロールすることが難しく、吐き戻してしまったりむせてしまったりするリスクが高いです。そのため、授乳のたびにしっかりゲップを出してあげることが大事といえるでしょう。
生後1ヶ月の赤ちゃん|ミルク量・授乳間隔・睡眠時間の目安について
生後3ヶ月の赤ちゃんの成長目安|体重・ミルク・睡眠・生活リズムについて
生後4ヶ月頃
生後4ヶ月を過ぎると、首がすわりはじめ、上半身の筋力が少しずつ発達していきます。赤ちゃん自身も胃腸の働きが向上し、ある程度は自然にゲップを出せるようになる子が多くなってきます。もちろん個人差がありますので、この時期になっても吐き戻しが続いたり、ゲップがうまく出せずにぐずったりする子もいます。
一方で、あまり空気を飲み込まなくなる赤ちゃんもいるため、赤ちゃんの様子を見つつ、合わせてあげることが大切です。
生後4ヶ月の赤ちゃんの成長とは?体重・授乳・睡眠時間やお世話のポイントを解説
生後5~6ヶ月頃
生後5~6ヶ月頃になると多くの離乳食をはじめる子が多く、赤ちゃんの姿勢や食事内容も変化します。離乳食はスプーンなどを使って食べさせるため、口の動きがさらに器用になり、空気の飲み込みも少しずつ減っていきます。さらに自分で寝返りをするようになると、お腹の圧迫や姿勢の変化で自然に空気が抜けることも増えてきます。
この時期になると、授乳直後のゲップが以前ほど重要ではなくなる赤ちゃんも多いです。しかし、激しく動いたあとにミルクを吐き戻す子もいるため、完全に卒業した区切りというよりは「ゲップをそこまで神経質にやらなくても大丈夫になってくる」と考えるとよいでしょう。
生後5ヶ月の赤ちゃんの成長とは?離乳食や睡眠のポイントを徹底解説
生後6ヶ月の赤ちゃんの成長とお世話|離乳食・睡眠・発達のポイントについて
ゲップ出しのサポートはいつまでしてあげるべき?
「もうゲップをさせなくてもいいのかな」と考える目安としては、授乳後に吐き戻しがほとんどなく、赤ちゃんが機嫌よく過ごしているかどうかが大切な指標です。また、授乳後に数分抱っこしてもゲップが出ないことが増え、赤ちゃんが苦しそうな様子もなければ、積極的にゲップを促す必要はあまりないといえるでしょう。
とはいえ、あくまでも月齢の目安や平均的な発達の話であって、赤ちゃんによっては卒業のタイミングが遅れることもあります。特に、吐き戻しの量が多かったり、授乳後の赤ちゃんが明らかに不快を訴えているようであれば、もうしばらく様子を見ながらケアを続けましょう。

ゲップが出ないときの対処法と注意点
赤ちゃんはゲップをあまり出さない状態が続くと、吐き戻しやお腹の張り、機嫌の悪さにつながることがあります。授乳の仕方や赤ちゃんの体調によってゲップの出やすさは変わるため、適切なケアを知ることが大切です。
授乳のペースや量を見直してみる
赤ちゃんによっては一気に大量のミルクや母乳を飲み込みすぎることで、空気も同時にたくさん含んでしまい、吐き戻しやお腹の張りにつながるケースがあります。
もし赤ちゃんが頻繁に吐き戻したり、ゲップが出づらそうにしていると感じたら、授乳のリズムや一度に与えているミルクの量を見直してみるのもよいでしょう。一度に飲む量を少し減らし、その分授乳回数を増やすやり方で様子をみると、ゲップの出方が改善する可能性があります。
赤ちゃんの体調をチェックする
ゲップが出にくい背景には、赤ちゃんの体調不良が関係していることもあります。たとえば鼻づまりがひどいと、授乳中に鼻呼吸がうまくできずに空気を余計に飲み込んでしまう場合があります。また、便秘や腹部膨満などがあると、お腹にガスが溜まりやすく、ゲップだけでなくおならも増えるかもしれません。
授乳をスムーズに行うためにも、普段から赤ちゃんの鼻づまりをこまめにケアする、便秘が続くときはかかりつけ医に相談するなど、赤ちゃん全体のコンディションを整えてあげることが大切です。
赤ちゃんの鼻水・鼻づまりで病院を受診する目安は?解消法・吸引のやり方とコツ
窒息の予防は万全に!
授乳後にゲップが出ないまま赤ちゃんが寝てしまうことはよくありますが、そのまま仰向けで寝かせると、万が一吐き戻しがあったときに窒息のリスクが高まります。完全に寝入る前に少し横向きにしておく、あるいはベビーベッドなどで上半身をわずかに高く保てるようにするなど、姿勢の工夫が必要です。また、布団やクッションの柔らかい凹みに顔を埋めてしまうと息苦しくなる可能性があるため、寝具は赤ちゃんの体格や動きに合わせて安全性の高いものを選びましょう。
医師への相談が必要なケース
生後数ヶ月を過ぎても授乳のたびに大量に吐き戻す、ミルクや母乳だけでなく胃液のようなものも勢いよく吐く、というような症状が見られる場合は、一度小児科を受診して相談するのがおすすめです。逆流性食道炎など、何らかの器質的な問題が潜んでいることも稀にあります。
加えて、赤ちゃんが苦しそうに唸り続けたり、寝ている間も頻繁に嘔吐するような場合も専門的な検査が必要かもしれません。ゲップにまつわる不安や疑問は、パパやママだけで抱えず、気軽にかかりつけ医に話をしてみると安心です。
5.よくあるQ&A|赤ちゃんのゲップに関する疑問を解決!

赤ちゃんのゲップについては、育児をしているとさまざまな疑問や不安が出てくるものです。ここでは、よくあるお悩みや質問にQ&A形式でお答えします。
Q.授乳後なかなかゲップが出ません。どうしたらいいですか。
A.まず抱っこする姿勢や背中のさすり方・叩き方を変えてみるのが効果的です。パパやママの肩に乗せる縦抱きだけでなく、膝の上で少し前かがみにさせたり、うつぶせに近い体勢にしてみたりすると、出やすくなることがあります。
それでも5分ほど粘って出なければ、一度横向きに寝かせて様子を見守ってあげましょう。
Q.げっぷは何回くらい出ればいいのでしょうか?
A.回数よりも、吐き戻しが少なく赤ちゃんが落ち着いていれば問題ないと考えて大丈夫です。 大きなゲップが一度出れば十分という子もいれば、小さめのゲップを何度か繰り返す赤ちゃんもいます。
ミルクを勢いよく飲む子は空気を多く飲み込みがちなので、ゲップも大きいのが出るかもしれませんし、母乳中心の子でゆっくり飲むタイプなら、そもそも空気量が少ないため小さなゲップで済むことも多いです。
Q.げっぷをせずに寝てしまったらどうすればいいですか?
A.赤ちゃんが授乳途中や授乳直後にスヤスヤ寝てしまうのはよくあることです。無理に起こしてゲップを出そうとすると、せっかく寝付いた赤ちゃんが泣いてしまって逆に落ち着かなくなる場合もあります。もし赤ちゃんが苦しそうな素振りを見せていないなら、そのまま寝かせても構いません。ただし、仰向けの姿勢で長時間寝かせると吐き戻したときに気道を塞ぐ恐れがあるため、頭をやや高くしてあげるか、横向きにするなどの工夫をしておきましょう。気になる場合は、いったん抱っこして背中をトントンし、数分だけ待ってみるのもひとつの方法です。
赤ちゃんのゲップは赤ちゃんの様子を見ながら無理なくケアしよう
赤ちゃんは授乳時に空気を飲み込みやすく、ゲップを促すことが大切です。ゲップが出ないと吐き戻しや誤嚥のリスクが高まるだけでなく、不快感で泣いてしまうこともあります。
新生児期から生後3ヶ月頃までは注意が必要ですが、生後4~6ヶ月を過ぎると自然に空気を抜きやすくなり、ゲップの必要性は減っていきます。ただし、卒業のタイミングには個人差があるため、赤ちゃんの様子を観察しながら無理なくサポートしましょう。
もしも頻繁な吐き戻しや苦しそうな様子があれば小児科医に相談することをお勧めします。ゲップのケアをしつつ、赤ちゃんの成長を楽しみながら育児に向き合っていきましょう。





