公開日 2025/04/14
【医師解説】赤ちゃんに抱き癖はつく?抱っこのメリットと正しい知識

目次
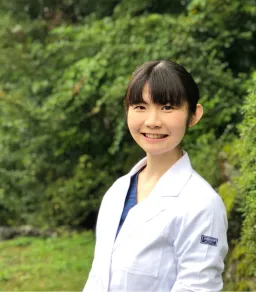
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
今回は多くのパパ・ママが心配される「抱き癖」について詳しくお話ししたいと思います。「抱っこしすぎると抱き癖がつく」と言われることがありますが、これは本当なのでしょうか?
赤ちゃんを抱っこすることの意味や効果について、医師の視点からお伝えします。赤ちゃんとの関わり方に不安を感じているパパ・ママの参考になれば幸いです。
「抱き癖」は本当に悪いの?知っておきたい最新の考え方
「抱き癖」という言葉をよく耳にしますが、これは一体何を意味するのでしょうか。抱き癖とは、赤ちゃんが常に抱っこを求め、抱っこしないと泣き止まなくなる状態を指します。
「抱っこしすぎると赤ちゃんが甘えん坊になる」「自立心が育たなくなる」という心配から、「抱きすぎないように」というアドバイスを耳にする方も多いと思います。
昔と今でこんなに違う!抱き癖に関するよくある誤解
「抱き癖」という考え方は、実は古い育児観に基づいています。以前は、赤ちゃんが泣いてもすぐに抱っこするのではなく、「泣いて強くなる」「我慢を覚える」という考え方が一般的でした。しかし、現代の発達心理学や小児医学では、こうした考え方は誤りであると指摘されています。
赤ちゃんが抱っこを求めたり泣いたりするのは、何かを伝えようとしているサインです。お腹がすいた、おむつが濡れた、眠い、不安で寂しい、など様々な理由があります。この時期の赤ちゃんは言葉を話せないため、こういったアクションでコミュニケーションを取っているのです。そのサインに応えてあげることは、赤ちゃんの情緒の安定や親子の信頼関係の構築に重要な役割を果たします。
医学と心理学が示す「抱っこ」の重要性とは
最新の研究では、生後間もない時期に十分な抱っこやスキンシップを受けた赤ちゃんは、情緒が安定し、自己肯定感が高く育つ傾向があることがわかっています。
特に生後6か月までの赤ちゃんは、「愛着形成期」と呼ばれる重要な時期です。この時期に親との間に安定した愛着関係を築くことが、後の情緒発達や対人関係の基礎になります。抱っこは愛着形成の大切な要素なのです。
いつまで続く?赤ちゃんが抱っこを求める時期の目安
赤ちゃんが常に抱っこを求める時期は永遠に続くものではありません。発達とともに自分で動けるようになると、興味の対象が広がり、自分から親から離れて探索活動を始めるようになります。多くの場合、ハイハイや歩行が始まる頃には、「抱っこ依存」は自然と解消されていきます。
生後6か月くらいまでの赤ちゃんが抱っこを強く求めるのは、まったく自然なことで心配する必要はありません。
赤ちゃんのメンタルリープとは?いつ起きるのか、原因や対策について解説

抱っこが赤ちゃんに与える驚くべき効果とは
赤ちゃんを抱っこすることには実は多くの良い効果があり、赤ちゃんの心と体の発達に大きな影響を与えるものなのです。
抱っこで脳と感覚が育つ!発達を助けるスキンシップの力
赤ちゃんを抱っこすると、皮膚への刺激、揺れの感覚、体温の伝わり、心音の聞こえなど、様々な感覚刺激が脳に伝わります。これらの刺激は脳の発達を促し、神経回路の形成を助けます。
特に前頭前皮質という部位は、ストレス調整や感情コントロールに関わる部分ですが、十分な身体接触を受けた赤ちゃんはこの部位の発達が良好であるという研究結果も出ています。
また、抱っこされている間、赤ちゃんは親の動きに合わせて自分の体を調整する必要があります。これが平衡感覚や筋肉の発達を促進します。赤ちゃんにとって、抱っこは楽しいエクササイズでもあるのです。
ベビーマッサージとは?6つの効果とやり方、注意点についても解説
泣いたら抱っこでOK!親子の信頼関係を深める理由
赤ちゃんは子宮の中で約10か月間、常に包まれて守られていました。生まれてからも、抱っこによって似たような安心感を得ることができます。特に新生児期は「第四の妊娠期」とも呼ばれ、赤ちゃんが子宮外の生活に適応するための期間です。この時期の抱っこは、赤ちゃんに大きな安心感を与えます。泣いたときに抱っこで応えてもらう経験を繰り返すことで、赤ちゃんは「自分の要求は聞き入れられる」「この世界は安全で信頼できる」という基本的信頼感を育みます。これは将来の自己肯定感や対人関係の基礎となる重要な心理的発達なのです。
赤ちゃんの体にもメリット!抱っこが健康をサポートする
抱っこには身体的な健康面でも良い効果があります。例えば、赤ちゃんを縦抱きすると、消化管が伸び、消化不良や吐き戻しの予防になります。また、親の体温が伝わることで体温調節を助け、皮膚の接触は免疫機能を高める効果も期待できます。
さらに、揺れの感覚は前庭感覚を刺激し、運動機能の発達を促します。親の呼吸や心拍のリズムを感じることで、赤ちゃん自身の生理的リズムも安定しやすくなります。こうした効果は、特に早産児や低出生体重児において顕著であることが研究で示されています。
抱っこは親のメンタルケアにも効果的!パパ・ママにもいいことが
抱っこは赤ちゃんだけでなく、パパやママにとっても大切な経験です。赤ちゃんを抱くと、親の体内でもオキシトシンというホルモンが分泌されます。このホルモンは「愛情ホルモン」とも呼ばれ、親子の絆を深め、育児への肯定的な感情を高める効果があります。
特に男性は女性と比べて、妊娠や出産を通じた赤ちゃんとの物理的なつながりがありません。パパが積極的に抱っこすることで、赤ちゃんとの絆を深め、父親としての実感を持ちやすくなります。家族全体の絆を強くするためにも、パパの抱っこタイムは大切です。
抱き癖を気にせずできる!赤ちゃんとの正しい抱っこのコツ

抱き癖を心配せずに、赤ちゃんの発達を促す適切な抱っこの方法について考えてみましょう。赤ちゃんの欲求に応えながらも、パパ・ママの負担を減らす工夫があります。
縦抱き?横抱き?月齢別おすすめの抱っこの方法
赤ちゃんを抱っこする方法には様々なバリエーションがあります。縦抱き、横抱き、腕の中で寝かせる抱き方、肩に乗せる抱き方など、赤ちゃんの好みや状況に合わせて変えてみましょう。
特に、お腹が張って苦しそうなときは縦抱きが効果的です。赤ちゃんの背中を軽くトントンすると、ガスが出やすくなります。寝かしつけるときは、ゆっくり揺らしながら横抱きにすると落ち着きやすい赤ちゃんが多いです。
また、赤ちゃんの月齢によって適した抱き方も変わります。首がすわる前は頭をしっかり支え、腰がすわってきたら腰抱きなど、発達に合わせた抱き方を取り入れていきましょう。
首すわりってどんな状態?いつ首がすわるのか、確認のポイントや促す運動をご紹介
抱っこひもを上手に活用!体の負担を軽くするポイント
常に手で抱っこを続けるのは体力的に大変です。そこで役立つのが抱っこひもです。適切に使用すれば、赤ちゃんにとっては抱っこと同様の安心感が得られ、パパ・ママは両手が使えるようになります。
抱っこひもを選ぶ際は、赤ちゃんの月齢に合ったものを選びましょう。新生児期は頭と首をしっかり支えられるタイプ、成長に合わせて前向き抱っこや背中おんぶができるタイプなど、様々な製品があります。
使用する際は、赤ちゃんの気道が確保され、M字開脚の姿勢になるように調整することが大切です。また、長時間の使用は赤ちゃんにも親にも負担になるので、適度な休憩を取りましょう。
ずっと抱っこしなくてOK!赤ちゃんの気持ちを読むコツとは?
赤ちゃんが抱っこを求めてぐずるタイミングには、ある程度のパターンがあります。お腹がすいたとき、眠いとき、退屈なときなどです。これらのタイミングを把握し、前もって対応することで、極端に長時間の抱っこを避けることができます。
例えば、お腹がすくタイミングの少し前に授乳の準備をしたり、眠くなるサインが出たら静かな環境で寝かしつけを始めたりすることで、激しくぐずる前に対応できます。また、赤ちゃんが起きている間は、適度な刺激(話しかける、歌を歌う、おもちゃで遊ぶなど)を与えることで、退屈からくる抱っこの要求を減らすことができます。
赤ちゃんの生活リズムを把握することは、パパ・ママの負担軽減につながります。ただし、生後間もない時期は不規則なことも多いので、あまり厳格なスケジュールで考えずに、赤ちゃんのペースに合わせることも大切です。
パパ・ママの負担を減らそう!周囲のサポートを上手に使う方法
育児は一人で抱え込むものではありません。特に抱っこに関しては、パパとママで分担することで、互いの負担を減らすことができます。また、祖父母や親戚、信頼できる友人などにも時々抱っこをお願いすることは、パパ・ママの休息時間を作るだけでなく、赤ちゃんが多様な人間関係を築く機会にもなります。
自治体の子育て支援サービスや、一時保育なども上手に活用しましょう。「抱き癖がつく」という心配から抱っこを制限するよりも、周囲のサポートを得ながら、必要なときに十分な抱っこをしてあげることの方が、赤ちゃんの健全な発達にとっても、パパ・ママの精神的・身体的健康にとっても良いことです。
抱っこに関するよくある悩みと対応策

抱っこに関して、多くのパパ・ママが抱えがちな悩みとその対応策についてお話しします。
抱っこしないと泣き止まない…そんなときはどうする?
赤ちゃんが抱っこしないと全く泣き止まない場合、パパ・ママは体力的にも精神的にも疲れてしまいます。このような場合は、まず赤ちゃんに他の不快感がないか確認しましょう。おむつが濡れていないか、暑すぎたり寒すぎたりしていないか、体調不良ではないかなどをチェックします。
それでも泣き止まない場合は、抱っこ以外の方法も試してみましょう。例えば、ゆりかごのようにゆっくり揺れるバウンサーやスイングを利用する、ホワイトノイズ(ドライヤーの音、掃除機の音など)を聞かせる、赤ちゃんを布で優しく包むスワドリング(おくるみ)などが効果的なこともあります。
また、赤ちゃんが特に泣きやすい時間帯には、パパとママで交代で対応したり、あらかじめ家事を済ませておいたりするなどの工夫も有効です。どうしても疲れてしまったときは、赤ちゃんを安全な場所に寝かせて、少し離れてリラックスする時間を取ることも大切です。
新生児(赤ちゃん)が寝ないときは?昼間や夜中に寝ないときの原因や寝かしつけのポイント
寝かしつけの悩み「布団に置くと起きる」問題の対処法
抱っこで寝かしつけると、赤ちゃんをベッドに移すときに起きてしまうことがよくあります。これは赤ちゃんの自然な反応で、安全確認の本能から来ています。
対策としては、赤ちゃんが深い眠りに入るまで(約20分程度)抱っこを続けてから移すことが効果的です。移すときは、あなたの体温が移った布やタオルをベッドに敷いておく、手をゆっくり引き抜く、などの工夫をしてみましょう。
また、寝かしつける際に毎回同じルーティンを作ることで、赤ちゃんに「これから寝る時間だ」という予測を与えることができます。例えば、薄暗い照明にする、同じ子守唄を歌う、絵本を読むなどの習慣を作りましょう。
赤ちゃんの“背中スイッチ”はいつまで続く?寝かしつけ成功のヒント
抱っこ疲れに要注意!パパ・ママの体調管理のススメ
赤ちゃんを抱っこし続けることは、腰や肩、腕に大きな負担がかかります。特に産後の身体が完全に回復していないママにとっては、正しい抱き方をしないと身体トラブルの原因になることも。
正しい抱き方のポイントは、赤ちゃんをできるだけ自分の体の近くに寄せること、腰を落とさず背筋を伸ばすこと、片方の腕だけで長時間抱かないことなどです。また、抱っこひもを使う際は、肩や腰にベルトが均等にフィットするように調整しましょう。
定期的にストレッチをしたり、可能であれば産後の整体などのケアを受けることも効果的です。何より、無理をせず、つらいときは周囲に助けを求めることが大切です。
よくあるQ&A|赤ちゃんの抱っこに関する疑問を解決!
赤ちゃんとの抱っこ生活の中で、パパ・ママが日々感じる小さな疑問や不安。「これって普通?」「どう対応すればいいの?」と悩むことも多いのではないでしょうか。
ここでは、赤ちゃんの抱っこに関してよく寄せられる質問にお答えします。医療や発達の知見に基づいて、安心して育児を続けるためのヒントをまとめました。
Q. 赤ちゃんが抱っこされると泣き止むのはなぜですか?
A. 赤ちゃんにとって抱っこは、子宮内にいた頃の安心感に近い体験です。親の体温、心音、呼吸のリズム、緩やかな揺れなどが赤ちゃんに安心感を与え、泣き止む効果があります。また、縦抱きの姿勢はお腹の不快感を和らげる効果もあります。
Q. いつまで抱っこを求められるのでしょうか?
A. 個人差はありますが、多くの赤ちゃんは歩行が始まる1歳前後から自分で行動範囲を広げていくようになり、常に抱っこを求める頻度は減っていきます。
ただし、疲れたときや不安なとき、体調が優れないときなどは、幼児期になっても抱っこを求めることがあります。これは自然な甘えの表現です。
Q. 抱っこをしすぎると赤ちゃんの背骨に悪影響はありませんか?
A. 正しい抱き方をしていれば、赤ちゃんの背骨に悪影響はありません。むしろ、適切な抱っこは筋力の発達を促します。
ただし、首がすわる前(生後3〜4ヶ月頃まで)は頭と首をしっかり支え、背骨に負担がかからないよう注意が必要です。
生後3ヶ月の赤ちゃんの成長目安|体重・ミルク・睡眠・生活リズムについて
生後4ヶ月の赤ちゃんの成長とは?体重・授乳・睡眠時間やお世話のポイントを解説
Q. 夜中に抱っこしないと寝ない赤ちゃんへの対応は?
A. 特に生後3ヶ月くらいまでの赤ちゃんは、昼夜の区別がついていないため、夜中に起きて抱っこを求めることは自然なことです。この時期は無理に訓練せず、できるだけ応えてあげましょう。徐々に夜間の授乳回数が減り、睡眠時間が長くなっていきます。
赤ちゃんの夜泣きはいつからいつまで?原因と乗り越えるための対策について
抱き癖は気にせず、赤ちゃんとの触れ合いの時間を大切にしよう
赤ちゃんが抱っこを求めるのは自然なことです。十分な抱っこやスキンシップは、赤ちゃんの情緒を安定させ、信頼関係を築くうえで重要な役割を果たします。
抱っこには脳の発達促進、消化機能の向上、親子の絆を深める効果など、多くのメリットがあります。成長とともに赤ちゃんは自ら探索活動を始めるため、「抱っこばかりで自立できない」という心配は不要です。
抱っこひもを活用する、家族と協力するなどして、無理のない範囲で赤ちゃんの要求に応えてあげましょう。大切なのは、赤ちゃんとの触れ合いを大切にしながら、パパ・ママ自身の負担を軽減する工夫をすることです。抱っこを通じて、親子のかけがえのない時間を楽しんでください。





