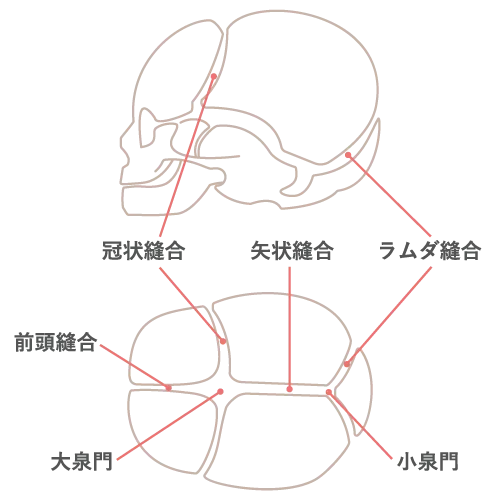公開日 2024/12/27
【医師解説】赤ちゃんのメンタルリープとは?いつ起きるのか、原因や対策について解説

目次
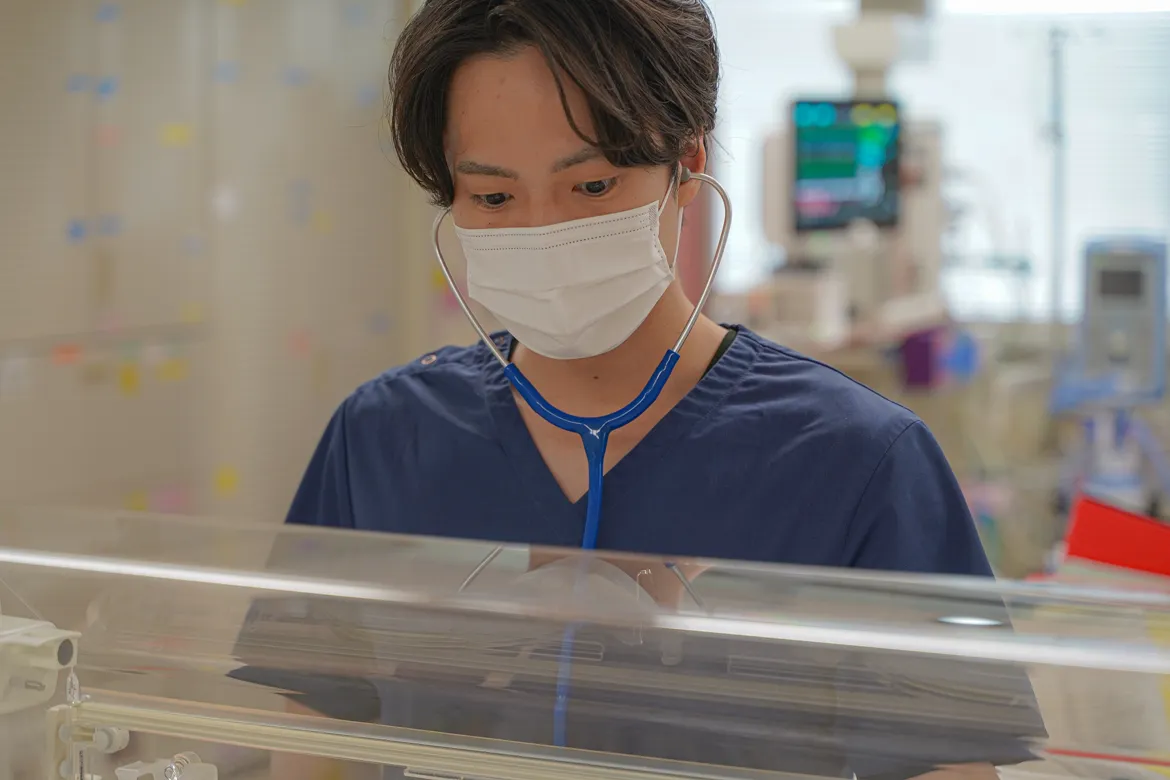
武田 賢大 先生
生後数ヶ月の赤ちゃんが突然ぐずったり、夜泣きが増えたりすることはありませんか?それは、赤ちゃんの脳の発達に伴う「メンタルリープ」が原因かもしれません。この記事では、赤ちゃんの成長過程で起こるメンタルリープについて解説します。メンタルリープとは何か、いつ頃起こるのか、赤ちゃんにどのような影響を与えるのか、そして親としてどう対応すべきかを詳しく見ていきましょう。
メンタルリープとは?
ここでは、赤ちゃんが生後間もない頃から約20ヶ月頃までの間に訪れる、脳と心の急速な発達過程「メンタルリープ」について解説します。はじめに、メンタルリープという概念がどのように発見・研究されてきたのか、そして赤ちゃんの発達においてなぜ重要なのかをわかりやすくお伝えします。
メンタルリープの発見と研究の歴史
メンタルリープとは、1990年代初頭にオランダ人研究者のプローイュ夫妻によって紹介された概念です。夫妻は、赤ちゃんの成長を長年観察する中で、特定の週齢に達するごとに赤ちゃんの認知や行動が飛躍的に変化し、同時期に一時的に不機嫌になったり、夜泣きなどの扱いづらさが増えることに気づきました。この規則性を示した著書『ワンダーウィーク』は世界中で注目を集め、同時に多くの育児専門家や研究者が追随するきっかけとなりました。
こうしてメンタルリープは「育児の指標」として知られるようになり、多くの研究者によって実証的なデータが蓄積されています。医学的に確立された概念ではなく、学術的な厳密性には議論もありますが、この概念によって「なぜ今、赤ちゃんが機嫌を損ねるのか」や「どのような新しい能力が花開こうとしているのか」を理解するヒントになります。小児医学というよりは、知育や幼児教育などの観点でみられる考え方で、監修している私自身も実際に育児を行うようになってから知った概念ですが、普段の小児科診療や一般的に乳幼児検診で用いられるお子さんの成長発達の指標と照らして見ても、乳幼児の発達が具体的にイメージしやすい考え方だと思います。
赤ちゃんの発達におけるメンタルリープの重要性
メンタルリープは、赤ちゃんの脳内で新たな知覚や思考パターンが構築され、物事の捉え方が質的に変化する時期を指します。これらのリープごとに、赤ちゃんは周囲の世界をより複雑に・多面的に理解できるようになります。親としてメンタルリープを理解することで、急なぐずりや夜泣きが「単なる気まぐれ」ではなく「新しいスキル獲得への過渡期」であることを把握しやすくなります。この理解は、赤ちゃんに対してより温かく、適切なサポートを行うための基盤となります。
赤ちゃんのメンタルリープはいつ起こる?時期別ガイド
ここでは、赤ちゃんが特定の週齢に達するたびに訪れると考えられるメンタルリープの概要と、その時期ごとの特徴を紹介します。乳幼児検診で求められる部分と対応する点についても見ていきたいと思います。赤ちゃんのメンタルリープは10個あると言われています。10個のリープについて順を追って説明し、各リープで赤ちゃんがどのような変化を見せるのかを解説します。
生後5週目頃:「五感が発達するリープ」で赤ちゃんの世界が広がる
「五感のリープ」では、赤ちゃんの視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚といった五感が急速に洗練されます。生後1ヶ月ちょっとの時期、赤ちゃんはこれまでよりクリアにお母さんやお父さんの顔を見つめ、声色の変化に反応し始めます。身近な人の顔を見ると笑顔を返したり、特定の音や光に一瞬戸惑ったりする様子が見られるでしょう。実際に目が合うかや周囲の音にびっくりするかという点は検診でチェックされる内容です。
さらに、肌触りの違いに敏感になったり、授乳中に好き・嫌いな姿勢やペースが出てきたりします。この時期には、赤ちゃんにとって心地よい刺激(柔らかなタオル、優しい音楽)を提供することで、五感を豊かに育む一助となります。
生後8週目頃:「パターンのリープ」で規則性を学ぶ時期
「パターンのリープ」では、赤ちゃんが「繰り返し」や「規則性」に気づき始めます。生後2ヶ月頃、赤ちゃんは自分の手足をじっと見つめ、繰り返し動かすことで身体の存在や動き方を学習します。これまで偶然だった手の動きが、少しずつ「同じ動作を繰り返す」という形でパターン化され、赤ちゃんにとって世界が一定のルールで動いているように感じられるのです。
親はこの時期、ゆったりとしたリズムの歌や、一定のテンポで揺らす抱っこなど、赤ちゃんがパターンを感じ取れる環境を整えてあげると良いでしょう。また、繰り返しの動作や音によって赤ちゃんが安心する様子も見受けられます。
生後12週目頃:「推移のリープ」で物事の流れを理解するステップ
「推移のリープ」は、生後3ヶ月頃に起こる世界理解の質的変化です。ここで赤ちゃんは、点として捉えていた事象を連続した流れとして理解し始めます。例えば、お母さんがお部屋に入ってきて話しかけ、笑いかけ、そして部屋を出ていく一連の動きを「流れ」として感じるようになります。
この段階では、声のトーンや動きのスピードの変化に興味を持つようになり、オモチャを差し出して揺らしてみたり、親が手を動かして見せたりすることで、赤ちゃんは「物事が移り変わる」様子を楽しめます。こうした経験は、後の因果関係理解や物の移動パターンの認知に繋がっていきます。発達指標的としては、一般的に声がする方に顔や目を向けたり、人の声で静かになったりする様子が見られる様子が見られる時期とされ、こういった内的変化を反映しているのかもしれません。
生後19週目頃:「出来事のリープ」で動きや現象に興味を持つ
「出来事のリープ」は、生後4〜5ヶ月頃、赤ちゃんが周囲で起こる一つ一つの行動や現象を、連続した出来事として理解し始める時期です。例えば、投げたボールが床を転がり、止まるまでの一連の流れを「面白い動き」として捉えるようになります。4ヶ月検診の時期であり、実際におもちゃなどであやすと、面白がって笑うか、気になるおもちゃや診察道具を自分の手で掴む様子が見られるかを確認しています。格段に周囲に対する興味や感情表現が豊かになっていることを実感します。
この段階で、赤ちゃんは物体が移動する軌跡をじっと追い、興味津々で見つめることがあります。これは、物理的な世界への関心が芽生えつつある証拠です。親は転がるボールや動くおもちゃを使い、赤ちゃんが「出来事」としての変化を理解できる環境を提供してみてください。
生後26週目頃:「関係のリープ」で人や物との距離感を学ぶ
「関係のリープ」は、生後6ヶ月頃に訪れます。この時期には、赤ちゃんが物と物、または人と人との「距離」や「関係性」をよりはっきりと理解し始めます。例えば、自分からお母さんまでの距離が分かるようになり、ハイハイなどの移動手段を使って親の元へ近づこうとします。
また、後追いが始まることも多く、親が姿を消すと不安になることがあります。これは、単なる泣きではなく、「親が自分から離れた」という空間的な関係を理解した上での反応です。空間を安全に整えて、赤ちゃんが安心して探索できるような環境を用意してあげましょう。
生後37週目頃:「分類のリープ」でものをカテゴリー分けして考える

「分類のリープ」は、生後9ヶ月弱頃で、赤ちゃんが物をカテゴリー分けして理解する力を身につけていく時期です。果物とおもちゃ、動物と人間など、物や存在を「似ているもの同士」でまとめて把握しようとします。
この段階では、赤ちゃんにいろいろな種類のおもちゃや簡単な絵本を見せると、同じカテゴリーに属する物を並べたり、共通点を見出そうとしたりする様子が見られることがあります。親は過度な説明は不要ですが、「これはワンワンだね」など簡潔な語りかけで赤ちゃんの理解をサポートすると良いでしょう。1歳に向けて単語を習得していく上でも重要な時期であると考えられます。
生後46週目頃:「順序のリープ」で行動の手順を覚える
「順序のリープ」は、生後約10〜11ヶ月頃に訪れます。赤ちゃんは物事をある特定の順番で行うことに興味を持ち、手順を踏んで組み立てる遊びに惹かれます。例えば、まだ一般的には不完全にしかできませんが、積み木を一つ一つ積み上げていく行為や、砂場で砂をシャベルで掬ってバケツに入れ、その後ひっくり返して形を作るといった、一連の手順が魅力的に映ります。遊んでいるおもちゃを取られたりすると不機嫌になる様子が見られる時期なのはこういったことが理由なのかもしれません。
こうした遊びを通して、赤ちゃんは「手順を踏むと結果が得られる」という因果関係や論理構造を体感的に理解します。親は赤ちゃんが根気よく挑戦できるよう、転がりにくい積み木や扱いやすいスコップなどの道具を用意すると良いでしょう。
生後55週目頃:「工程のリープ」で物事を段階的に進める力を育てる
「工程のリープ」では、生後1歳1ヶ月前後、赤ちゃんはより複雑な過程や段階を意識するようになります。例えば、食事の後片付けをする、ブロックを組み立ててから壊す、または絵本を開いてページをめくりながら順序立てて眺めるといった、一連の工程に興味を示します。
この時期には「行動を完成させる満足感」を得ようとし、物事を自己完結的に処理しようとする様子が見られます。実際に検診でも自分で包み紙をとって食べたり、コップの中の小さなものを取り出したり、自分で問題解決をする様子が見られるかを見られます。親は褒めたり、手順を少し手伝ってあげたりしながら、赤ちゃんが自身の力で最後までやり遂げる喜びを感じられるようサポートしましょう。
生後64週目頃:「原則のリープ」でルールや法則性を試す
「原則のリープ」は、生後約1歳3ヶ月頃に起こり、赤ちゃんは行動やルールの背後にある「原則」を理解し始めます。例えば、「物を落とせば下に行く」「ドアを開けると部屋に入れる」といった法則性を試すようないたずらが増えることがあります。これは単なる悪戯ではなく、「世界が一定の原則で動いている」ことを学ぼうとしているサインです。
実際に簡単な要求や命令を理解できるようになってくる時期です。親は、大けがにつながらない範囲でこの実験的行動を見守り、危険な場合にはやんわりと制止してルールを示すことが重要です。そうすることで、赤ちゃんは「こうするとこうなる」という原則的な理解を深め、自ら行動をコントロールする力を育てていきます。
生後75週目頃:「体系のリープ」で社会のしくみを学び始める
「体系のリープ」は、生後1歳半過ぎ頃、赤ちゃんが周囲の環境や社会にある体系的なしくみを徐々に把握する時期です。場所ごとに異なるルールがある、保育園と自宅と公園では人々の振る舞いが違う、といったことを感じ取り、状況に応じた行動を自分なりに選択しようとします。
この時期には、親が「ここでは走っていいけれど、あそこでは静かにしようね」といった簡単な説明を行うことで、赤ちゃんは環境ごとの違いを学び、自分なりに行動を調整します。こうして赤ちゃんは、より高度な社会性や環境適応力を獲得していくのです。
メンタルリープが赤ちゃんに与える影響とは?
続いては、メンタルリープに伴う赤ちゃんの情緒面や行動面の変化に焦点を当てます。リープ期には赤ちゃんが一時的に不安定になることが多くなります。その理由をしっかり理解し、具体的な対処法を知っておくことが大切です。
赤ちゃんがぐずる理由と解決法
メンタルリープが訪れると、赤ちゃんは新しい世界の捉え方に挑戦します。そのため、戸惑いや不安を感じ、泣く回数が増えたり抱っこをせがんだりします。これは決してわがままではなく、未知の世界へ踏み出すための「助けてサイン」です。
親は、赤ちゃんに優しく話しかけ、抱きしめ、スキンシップを通じて安心感を与えましょう。赤ちゃんが怖がらない程度の新しい刺激を少しずつ与え、慣れるまで穏やかに付き合うことが大切です。
夜泣きや睡眠トラブルが増える理由とその対策
リープ期には、睡眠パターンが乱れることもしばしばです。夜泣きが増えたり、昼寝の時間がバラバラになるかもしれません。これは脳内での情報処理が活発化し、赤ちゃんが新しいスキル獲得に集中しているためと考えられます。対処法としては、できるだけ生活リズムを整え、同じ時間帯に睡眠や食事を提供することが効果的です。寝かしつけ前に静かな音楽を流したり、薄暗い照明を使ったりすることで、赤ちゃんが眠りやすい環境を整えてください。
赤ちゃんの夜泣きはいつからいつまで?原因と乗り越えるための対策を解説
黄昏泣き(コリック)はいつからいつまで続く?5つの対処方法と対策グッズを紹介
一時的な発達の後退?焦らず見守るべき理由
あるリープ期には、先週までできていた動作や習慣が一時的にできなくなることがあります。これは、さらに新しいスキルを身につけるための「準備期間」としての後退であり、心配する必要はありません。親は「前できたのに、なぜできなくなったの?」と焦らず、赤ちゃんが自然と新しい能力を獲得するまで穏やかに待ち、見守りましょう。そのうち赤ちゃんは、自分なりに理解を深めた上で、より高度なスキルを身につけて戻ってきます。
メンタルリープ期の赤ちゃんへの対応

メンタルリープを迎える赤ちゃんに対して親が心がけたい具体的な接し方や環境作りを紹介します。それぞれの段階で赤ちゃんが学び取りたいことをサポートし、安全かつ安心感に満ちた環境を整えることで、より健やかな成長を促していけるでしょう。
子どもの成長をそっと見守り、寄り添う
メンタルリープは赤ちゃんにとって、未知の世界への一歩を踏み出す冒険の時期です。親は、その挑戦を見守り、無理に押し付けたり急がせたりせず、赤ちゃんが自ら関心を示したときにそっとサポートしてください。成功や失敗に対して厳しく評価する必要はなく、「頑張ってるね」「すごいね」と優しく声をかけることで、赤ちゃんの自信を育てましょう。
不安定な時期だからこそ!安心感を与えるスキンシップと環境作り
リープ期は赤ちゃんが不安定になりがちな時期です。やさしく抱きしめたり、背中をさすったり、肌と肌の触れ合いを大切にして安心感を与えます。また、過度な刺激を避け、静かで落ち着く空間を用意しましょう。
柔らかな色合いの布製玩具、淡い照明、落ち着いた音楽など、赤ちゃんにとって心地よい要素を取り入れることで、心が安定し、メンタルリープで得た新しい学びを吸収しやすくなります。
メンタルリープ中でも規則正しい生活リズムを
メンタルリープ中でも、ある程度の規則正しさは赤ちゃんの安心につながります。食事やお昼寝、夜間睡眠の時間帯を大きく変えないようにし、生活のリズムを維持しましょう。また、赤ちゃんの発達段階に合わせた遊びを提供することで、リープ期間中に新たに身につけようとしているスキルがスムーズに発揮されやすくなります。
赤ちゃんが「自分でできる」を感じる瞬間を大切に
リープを経て赤ちゃんは徐々に自立心を芽生えさせます。全てを手伝うのではなく、赤ちゃんが自分で挑戦する余地を残してあげましょう。特に後半のリープ(原則、体系など)では、赤ちゃんは物事の原理や仕組みを理解し、自分なりに行動を決めようとします。危険がない範囲で「やりたい」という気持ちに応え、上手くいかないときは手助けを惜しまず、上手くできたら「うまくいったね」と肯定的な声をかけてあげてください。
メンタルリープに関するよくある質問
メンタルリープは赤ちゃんの成長とともに親御さんも悩みが増える時期。「夜泣きが増えるのはなぜ?」「抱き癖はつく?」など、戸惑うことも多いでしょう。ここでは、よくある質問にお答えし、赤ちゃんとの接し方や注意点をわかりやすく解説します。
Q. メンタルリープ中のやってはいけない対応はありますか?
A. 怒鳴ったり、無視したりするのは避けましょう。赤ちゃんの混乱を受け止め、共感的に接することが大切です。
Q. メンタルリープの時期でもぐずらないのですが大丈夫でしょうか?
A. 個人差があり、必ずしもぐずる訳ではありません。しかし、この時期は発達の節目なので、赤ちゃんの小さな変化に気を配りましょう。
Q. 一日中抱っこすると抱き癖はつきますか?
A. 発達の揺らぎには、抱っこなどで安心感を与えることが大切です。程よい抱っこは構いませんが、一日中は避けたほうが良いでしょう。メンタルリープは、赤ちゃんの飛躍的な成長を支える重要な過程です。その節目を乗り越えるには、ママ・パパが赤ちゃんの気持ちに共感し、安全基地となることが不可欠ですね。また、赤ちゃんが安心して過ごし、学びやすいように工夫された生活環境づくりと、発達に適した刺激を与えることも効果的です。赤ちゃんの発達段階に合わせて、思慮深く対応していきましょう。
メンタルリープを理解して、赤ちゃんの成長を見守ろう
メンタルリープは、生後5週目頃の五感のリープから始まり、約20ヶ月頃まで合計10回起こると考えられています。五感の洗練、パターン認識、推移や出来事、関係・分類・順序・工程・原則・体系といった段階を経ることで、赤ちゃんは世界をより深く、複雑に理解していきます。この過程では、赤ちゃんが不安定になったり、睡眠が乱れたり、時に一時的な後退が見られることもあるでしょう。しかし、それらは新たな発育過程に移行していることの前兆でもあります。スキンシップを重ね、安心できる環境を用意し、規則正しい生活リズムを維持しながら、赤ちゃんのペースに合わせて穏やかに見守ることが大切です。メンタルリープを理解し、赤ちゃんの新しい一面が花開く瞬間を、親子でともに楽しんでいきましょう。