公開日 2025/04/11
【医師解説】おしゃぶりはいつまで使ってOK?やめる時期とコツを解説

目次
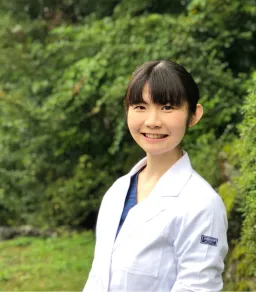
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
生まれたばかりの赤ちゃんを育てるママ・パパにとって、おしゃぶりは赤ちゃんを落ち着かせるための強い味方です。しかし、「いつまで使わせていいの?」「長く使うとどんな影響があるの?」という疑問を持っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。この記事では医師の立場から、おしゃぶりの適切な使用期間や卒業させるためのコツ、そして長期使用によるリスクについて詳しく解説します。赤ちゃんの成長を見守りながら、無理なくおしゃぶりを卒業させるための参考にしていただければ幸いです。
赤ちゃんにとって「おしゃぶり」はなぜ必要?
おしゃぶりは赤ちゃんの発達と安心感をサポートする重要なアイテムです。まずは、なぜ赤ちゃんにとっておしゃぶりが必要なのか、その理由について見ていきましょう。
なぜ泣き止む?おしゃぶりが赤ちゃんに与える安心感
赤ちゃんには生まれつき「吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)」という反射があり、口に触れたものに本能的に吸い付きます。これは母乳やミルクを飲むための反射ですが、吸うという行為自体が赤ちゃんに心地よさと安心感を与えるのです。
おしゃぶりはこの吸いたいという本能的な欲求を満たし、赤ちゃんをリラックスさせる効果があります。特に生後直後から数か月の赤ちゃんにとって、吸うという行為は大きな慰めとなります。
ママやパパの腕の中でも泣き止まない時、おしゃぶりが魔法のように赤ちゃんを落ち着かせることがあるのはこのためです。
モロー反射はいつからいつまで?激しいときの対処法3つと動きが似ている疾患を解説
バビンスキー反射って何?赤ちゃんの発達チェックポイントを解説
痛みや不安もやわらげる!医療処置でも活躍するおしゃぶりの効果
予防接種や採血など、痛みを伴う医療処置を受ける際に、おしゃぶりを使用することで赤ちゃんの痛みや不安を和らげる効果があります。
情緒発達にも効果的? おしゃぶりが育む「自分で落ち着く力」
赤ちゃんはおしゃぶりを通して、自分で気持ちを落ち着ける方法を学びます。これは将来的に感情のコントロールや自己調整力を発達させる上で重要な経験となります。
夜泣きや機嫌の悪い時など、赤ちゃん自身がおしゃぶりを求めることで、自分なりのストレス対処法を身につけていくのです。この自己調整の学習は赤ちゃんの情緒発達において重要な一歩と言えるでしょう。
赤ちゃんのメンタルリープとは?いつ起きるのか、原因や対策について解説
赤ちゃんの夜泣きはいつからいつまで?原因と乗り越えるための対策について

おしゃぶりはいつまでOK?年齢別の使用目安と卒業のタイミング

おしゃぶりの使用期間について、「絶対にこの年齢までに卒業させなければならない」という固定的な答えはありません。しかし、一定の目安もあります。年齢別におしゃぶりとの関係を見ていきましょう。
0歳から2歳までの使い方|成長とともに変わるおしゃぶりの役割
生後0〜6ヶ月の赤ちゃんは、おしゃぶりを必要とする場合も多いです。この時期は吸啜反射が強く、おしゃぶりを使うことで赤ちゃんが落ち着き、睡眠の質が向上することも多いです。
生後6ヶ月〜1歳になると、徐々に自分の指を使って口に入れる動きが増えてきます。この頃になると、常時おしゃぶりが必要な状況から、特定の場面(寝るとき、ぐずったときなど)に限定して使用するようになるのが自然な流れです。
1歳〜2歳になると、言葉の発達が活発になり、自己主張も増えてきます。この時期からは、おしゃぶりの使用を徐々に減らし、他のコミュニケーション方法や自己表現を促すことが大切です。
赤ちゃんの睡眠時間の目安とは?まとまって寝るようになるのはいつから?月齢別に解説
おしゃぶり卒業の目安はいつ?2歳までに始めたい理由とは
2歳頃までにおしゃぶりを卒業させることを推奨されています。2歳を過ぎてからの長期使用は、後述するようなリスクが高まるためです。
ただし、急に取り上げるのではなく、1歳半頃から徐々に使用頻度を減らしていくことが理想的です。段階的にアプローチすることで、お子さんのストレスが軽減することもあります。
おしゃぶり卒業には個人差がある!子どものペースを大切に
子どもの発達には個人差があり、おしゃぶりへの依存度も様々です。中には早くから興味を示さなくなる子もいれば、強い愛着を持つ子もいます。
重要なのは、お子さんの発達ペースや性格を尊重しながら、少しずつ卒業に向けたステップを踏むことです。無理に取り上げることでかえって不安や反発を強めてしまうこともあります。
お子さんの様子を見ながら、適切なタイミングを見計らうことがママ・パパの大切な役割です。
おしゃぶりを長く使い続けるリスク|歯並び・発音・言語への影響
2歳を超えてもおしゃぶりを頻繁に使用し続けると、いくつかのリスクが高まって来てしまいます。特に3歳以降も使い続ける場合は注意が必要です。
まず、歯並びへの影響が挙げられます。おしゃぶりを長期間使用すると、上の前歯が前方に突き出したり(上顎前突)、前歯の間に隙間ができたり(開咬)する可能性が高まります。
また、口の筋肉の発達が妨げられ、発音に影響が出ることもあります。特に「サ行」や「タ行」などの発音が不明瞭になりやすいです。
さらに、おしゃぶりを常に口に入れていると会話の機会が減り、言語発達の遅れにつながる可能性もあります。
これらのリスクを考慮すると、2歳までに卒業の準備を始め、遅くとも3歳頃までには完全に卒業させることが望ましいでしょう。
赤ちゃんの歯が生える時期と歯固めの選び方|歯磨きを始めるための基本ポイント
おしゃぶりをやめさせたい!スムーズに卒業するための実践ステップ

おしゃぶりに強く依存している子どもの場合、どのように卒業させていけばよいのか悩むことも多いでしょう。ここでは、無理なくおしゃぶりを卒業させるための具体的なステップをご紹介します。
いきなりやめさせないで!徐々に減らす「段階的アプローチ」
突然おしゃぶりを取り上げるのではなく、段階的に使用機会を減らしていくことがポイントです。最初は日中のみ制限し、寝る時だけ使用するようにしましょう。
例えば、「おうちの中ではおしゃぶりはお休み」「お外に出かける時だけ」など、使用するシーンを限定していきます。これにより、子どもも少しずつおしゃぶりなしの時間に慣れていきます。
おしゃぶりを使わない時間が増えたら、そのことをしっかり褒めてあげることも大切です。「おしゃぶりなしでもお話上手だね」「おしゃぶりなしでも遊べてえらいね」など、ポジティブな声かけをしましょう。
2歳から使える!言葉とコミュニケーションで理解を深めるコツ
2歳前後になると、簡単な説明を理解できるようになります。「おしゃぶりは赤ちゃんのものだけど、○○ちゃんはもうお兄ちゃん(お姉ちゃん)になったね」といった会話を通して、成長の過程としておしゃぶりを卒業する意味を伝えましょう。
絵本や人形を使って、おしゃぶりを卒業する様子を演じてみるのも効果的です。「くまさんもおしゃぶりを卒業したんだって」など、子どもが共感できるストーリーを作ってみてください。
「おしゃぶり卒業カレンダー」を作って、卒業までの日数をカウントダウンする方法も子どもの達成感につながります。シールを貼ったり、印をつけたりして、視覚的に分かりやすく進捗を示しましょう。
おしゃぶり卒業は“お祝いイベント”に!前向きな演出アイデア
おしゃぶりの卒業を特別なイベントとして演出することで、子どもにとってポジティブな経験にすることができます。例えば「おしゃぶり卒業式」を行い、小さな贈り物や証書を渡すのも良いでしょう。
「おしゃぶり妖精」や「サンタさん」にプレゼントと交換するという方法も人気があります。おしゃぶりを枕元に置いて寝ると、翌朝には小さなプレゼントに変わっているという演出です。
卒業を記念して家族で外食したり、特別な遊びの時間を設けたりするのも、子どもにとって嬉しい思い出になります。「おしゃぶりを卒業したから、お祝いしようね」という前向きなメッセージを伝えましょう。
どうしてもやめられない時の対処法
どうしてもおしゃぶりを手放したがらない場合は、一度立ち止まって考え直すことも大切です。無理に取り上げることでストレスが増し、指しゃぶりなど別の習慣に移行してしまうこともあります。
夜間だけ使用を許可するなど、柔軟な対応も検討しましょう。睡眠の質が著しく低下するようであれば、一時的に戻してもよいでしょう。長い目で見れば、お子さんの成長とともに自然と手放すケースも多いです。
どうしても心配な場合は、小児歯科医や小児科医に相談するのも一つの選択肢です。専門家のアドバイスを受けることで、お子さんの状況に合わせた対応が可能になります。
よくあるQ&A|おしゃぶりに関する疑問を解決!
ここでは、ママ・パパからよく寄せられるおしゃぶりに関する質問にお答えします。
Q. おしゃぶりをあまり使用してはいけないと聞きますが、使用する上でのメリットとデメリットを教えてください。何歳頃までに止めさせればいいですか?
A. おしゃぶりのメリットとしては、赤ちゃんに安心感を与える、自己鎮静力を育む、痛みを感じる医療処置の際に気を紛らわせる効果がある、などが挙げられます。
一方、デメリットとしては、長期使用による歯並びへの影響、言語発達への影響などがあります。
多くの専門家は2歳頃までの使用を推奨しており、遅くとも3歳までには完全に卒業させることが望ましいでしょう。ただし、急に取り上げるのではなく、1歳半〜2歳頃から徐々に減らしていくことをお勧めします。
Q. おしゃぶりを長期使用すると大人になってからの歯並びに影響は出ますか?
A. 4歳以降までおしゃぶりを頻繁に使用し続けると、永久歯の歯並びにも影響が残る可能性があります。特に上の前歯が前に突き出す「上顎前突」や、前歯が閉じない「開咬」といった問題が生じやすくなります。
ただし、3歳頃までに卒業できれば、多くの場合は乳歯列の間に自然と改善されることが多く、永久歯への影響は最小限に抑えられると考えられています。
気になる場合は、小児歯科を受診して専門的な評価を受けることをお勧めします。早期に対応することで、将来的な矯正治療の必要性を減らせる可能性があります。
Q. おしゃぶりの代替品はありますか?
A. おしゃぶりの代わりになるものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- お気に入りのぬいぐるみやタオル:触れることで安心感を得られるアイテムです。
- 歯がため:歯の生え始めの不快感を和らげるだけでなく、噛む満足感も得られます。
- 音楽や子守唄:聴覚からの刺激で赤ちゃんを落ち着かせる効果があります。
- 抱っこやマッサージ:スキンシップによる安心感は非常に効果的です。
- 絵本の読み聞かせ:寝る前のルーティンとして定着させると、おしゃぶりの代わりになることがあります。
おしゃぶりを卒業する過程では、これらを組み合わせて使うことで、徐々におしゃぶりへの依存を減らしていくことができます。お子さんの好みや反応を見ながら、最適な組み合わせを見つけてみてください。
おしゃぶりとの上手な付き合い方と卒業への道のり
おしゃぶりは、赤ちゃんの安心感や自己鎮静を助ける重要なアイテムですが、2歳を過ぎると歯並びや言語発達に影響が出る可能性があるため、多くの専門家は2歳頃までの使用を推奨しています。その後は段階的に使用機会を減らし、子どもの理解を促しながら卒業を進めましょう。焦らず子どものペースを尊重し、必要に応じて専門家に相談するのも良い方法です。
おしゃぶりの使用は育児の一部であり、良し悪しの二択ではなく、成長や個性に合わせた対応が大切です。ママやパパがリラックスして育児を楽しむことが、赤ちゃんの健やかな成長につながります。





